働く人にとって「休みを取れるかどうか」は大きな関心ごとです。
中でも「年次有給休暇(以下、有給休暇)」は、労働基準法で認められた労働者の権利であり、正社員だけでなくアルバイトやパートにも適用されます。
しかし、付与の条件や取得の仕組みを正しく理解していないと、会社と労働者の間でトラブルになることも少なくありません。
この記事では、有給休暇の基本ルールを労働基準法に基づいて整理し、わかりやすく解説します。
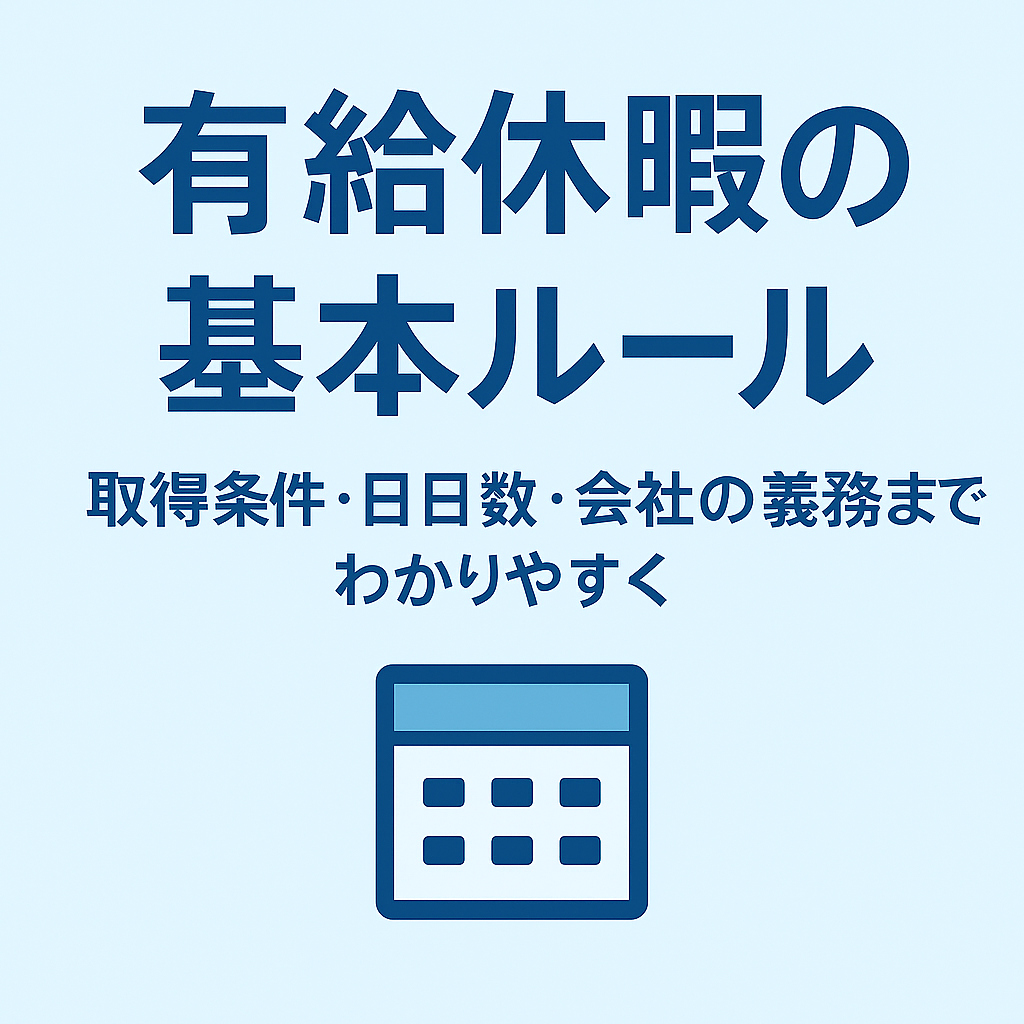
有給休暇とは?
有給休暇とは、労働者が休んでもその分の賃金が支払われる休暇制度です。
労基法第39条により、労働者の心身の健康保持や生活の安定を目的として認められています。
ポイントは👇
- 労働者にとって「権利」であり、会社の裁量ではない
- 正社員、契約社員、アルバイト、パートなど雇用形態にかかわらず適用される
- 勤続年数や労働日数に応じて日数が付与される
有給休暇が付与される条件
有給休暇を取得するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 雇用開始から6か月以上継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上を出勤していること
この条件を満たした場合、原則として 10日間の有給休暇 が付与されます。
付与日数の増え方
有給休暇の日数は勤続年数に応じて増えていきます。
週5日勤務の場合の例を示します👇
- 6か月勤務:10日
- 1年6か月:11日
- 2年6か月:12日
- 3年6か月:14日
- 4年6か月:16日
- 5年6か月:18日
- 6年6か月以上:20日(上限)
👉 勤続が長くなるほど有給休暇が増える仕組みです。
アルバイト・パートの場合
週の労働日数や労働時間が少ない人も、勤務日数に応じて比例付与されます。
例えば週3日勤務の場合👇
- 6か月勤務:5日
- 1年6か月:6日
- 3年6か月以上:9日
👉 「正社員しか有給がない」と思っている人もいますが、それは誤解です。
有給休暇の取得ルール
1. 労働者の請求で取得できる
有給休暇は労働者が「この日に休みたい」と請求すれば取得できます。
会社の承認制ではありません。
2. 会社が変更できる場合(時季変更権)
ただし、会社に「事業の正常な運営を妨げる場合」は、別の日に変更させることができます。
これを「時季変更権」といいます。
3. 時効は2年
有給休暇は取得しないと消えてしまいます。
付与から2年経過すると時効により消滅します。
会社の義務と実務上の注意点
- 2019年からは「年5日の取得義務」が法律で定められました。
- 会社は従業員の有給取得状況を管理し、年5日以上を必ず取らせなければなりません。
- 有給休暇の買い取りは原則禁止。ただし退職時など例外あり。
違反した場合のリスク
- 労働基準監督署から是正勧告
- 従業員からの未消化有給の損害賠償請求
- 「有給が取れないブラック企業」として評判悪化
👉 有給休暇は労働者の健康や生活に直結するため、違反は重大なリスクになります。
まとめ
- 有給休暇は労基法で認められた労働者の権利
- 6か月勤務・出勤率8割以上で10日付与
- 勤続年数に応じて日数は増加、最大20日
- アルバイト・パートも比例付与される
- 時効は2年、会社には年5日の取得義務がある
👉 有給休暇を正しく理解することは、働きやすい職場づくりや自分の権利を守るために不可欠です。
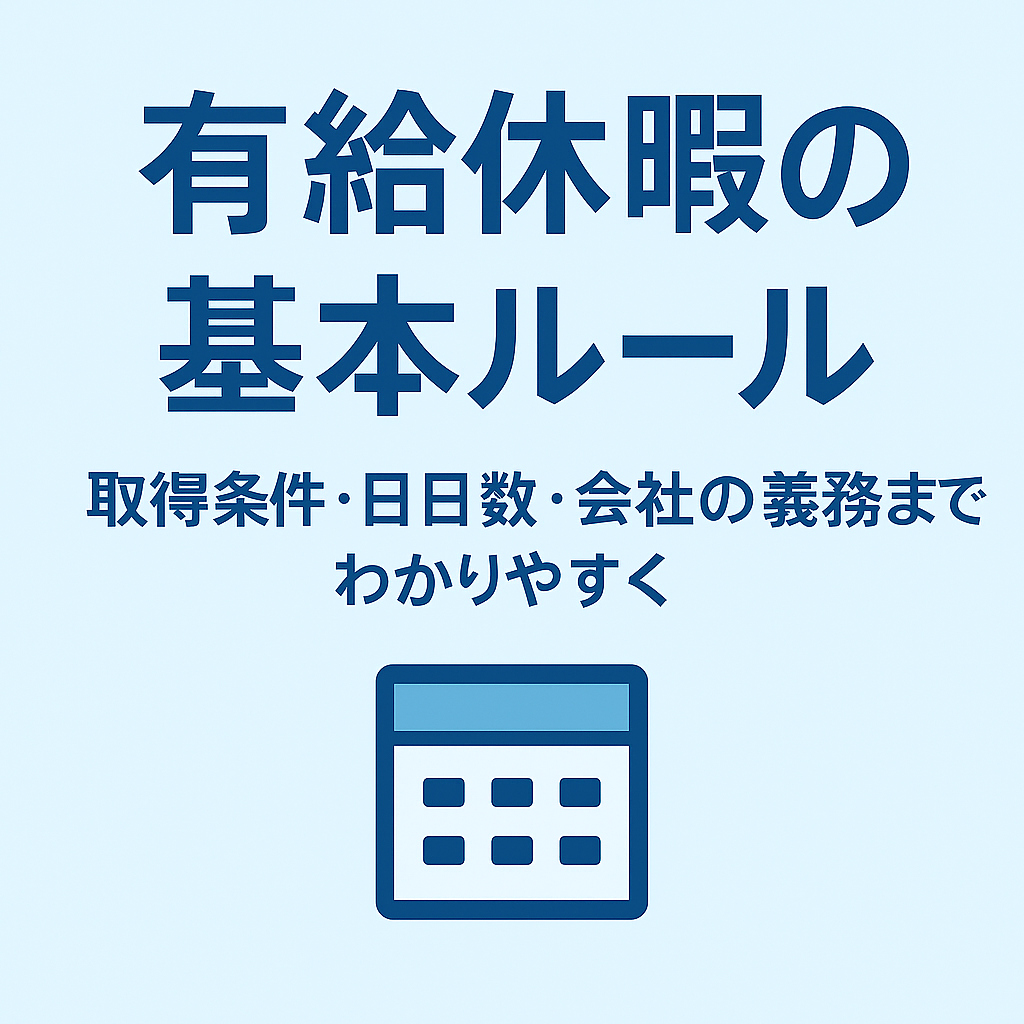

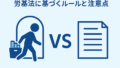
コメント