会社員として働いていると「残業代」という言葉はよく耳にします。
しかし、「実際にどうやって計算されているのか?」を正確に理解している人は少なく、労働トラブルの原因になりやすい分野です。
この記事では、労働基準法に基づく残業代の基本ルール、割増率、計算方法、実務でよくある注意点までを丁寧に解説します。
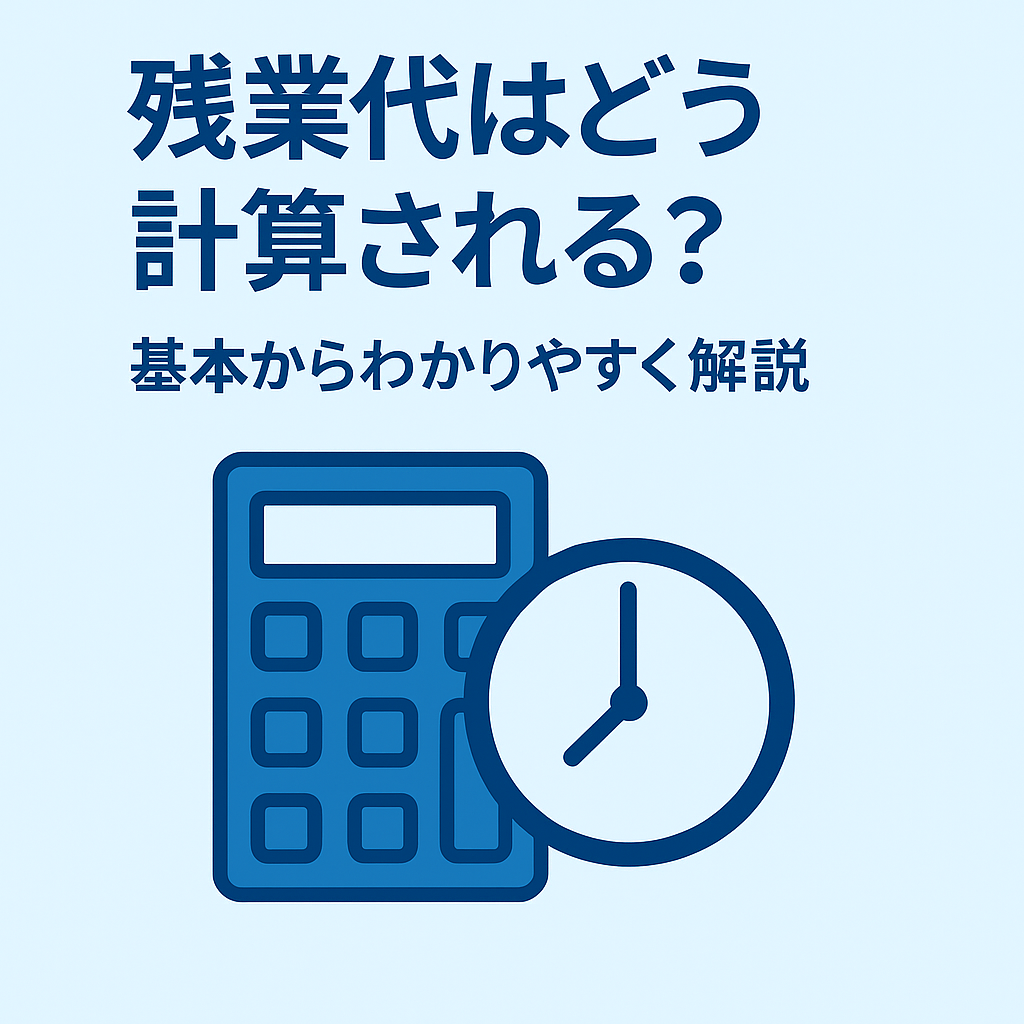
残業とは?
労働基準法では、次の時間を超えて働いた場合を「残業(時間外労働)」と定めています。
- 1日:8時間
- 1週間:40時間
この法定労働時間を超えて働いた場合、会社は労働者に「割増賃金」を支払わなければなりません。
また、休日労働や深夜労働も特別な割増が発生します。
割増率の基本
労基法で定められた割増率は以下の通りです👇
- 時間外労働(残業):25%以上
- 休日労働:35%以上
- 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上
- 時間外労働が月60時間を超える部分:50%以上
👉 つまり、9時~17時の方が22時以降に残業をすると「25%+25%=50%増」となります。
残業代の計算方法
残業代は、基礎賃金 × 割増率 × 残業時間 で求めます。
基礎賃金とは?
残業代の基礎に含まれるのは「基本給+各種手当(役職手当・職務手当など)」です。
一方で、通勤手当・家族手当・住宅手当など一部の手当は含まれません。
計算例
例えば、基本給25万円・所定労働時間160時間の人が、平日に10時間残業した場合:
- 時給換算=25万円 ÷ 160時間 = 1,562円
- 割増後時給=1,562円 × 1.25 = 1,952円
- 残業代=1,952円 × 10時間 = 19,520円
👉 このように明確に計算できるため、労使トラブルを避けるためには正しい理解が不可欠です。
実務で注意すべきポイント
1. みなし残業・固定残業代
あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含める制度。
ただし「超えた分」を支払わないのは違法です。
2. サービス残業
「残業代を申請しにくい」「上司が認めない」などの理由で支払われないケースは違法。
労働基準監督署に申告すれば是正されます。
3. 36協定との関係
残業を命じるには、会社と労働者代表との間で36協定を締結し、労基署に届け出る必要があります。
協定がなければ、そもそも残業はさせられません。
違反した場合のリスク
会社が残業代を正しく払わなかった場合、次のリスクがあります。
- 過去3年分の未払い残業代を請求される
- 労基署から是正勧告を受ける
- 悪質な場合は刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
👉 残業代未払いは大きなリスクであり、企業にとっても避けるべき問題です。
まとめ
- 残業とは「1日8時間・週40時間」を超える労働
- 残業代の割増率は25%以上、休日は35%、深夜は25%
- 月60時間を超える残業には50%の割増
- 基礎賃金をもとに計算し、一部の手当は含まれない
- サービス残業や固定残業代の不正運用は違法
👉 残業代のルールを正しく理解することは、労働者の権利を守るだけでなく、企業にとってもトラブルを防ぐ第一歩です。
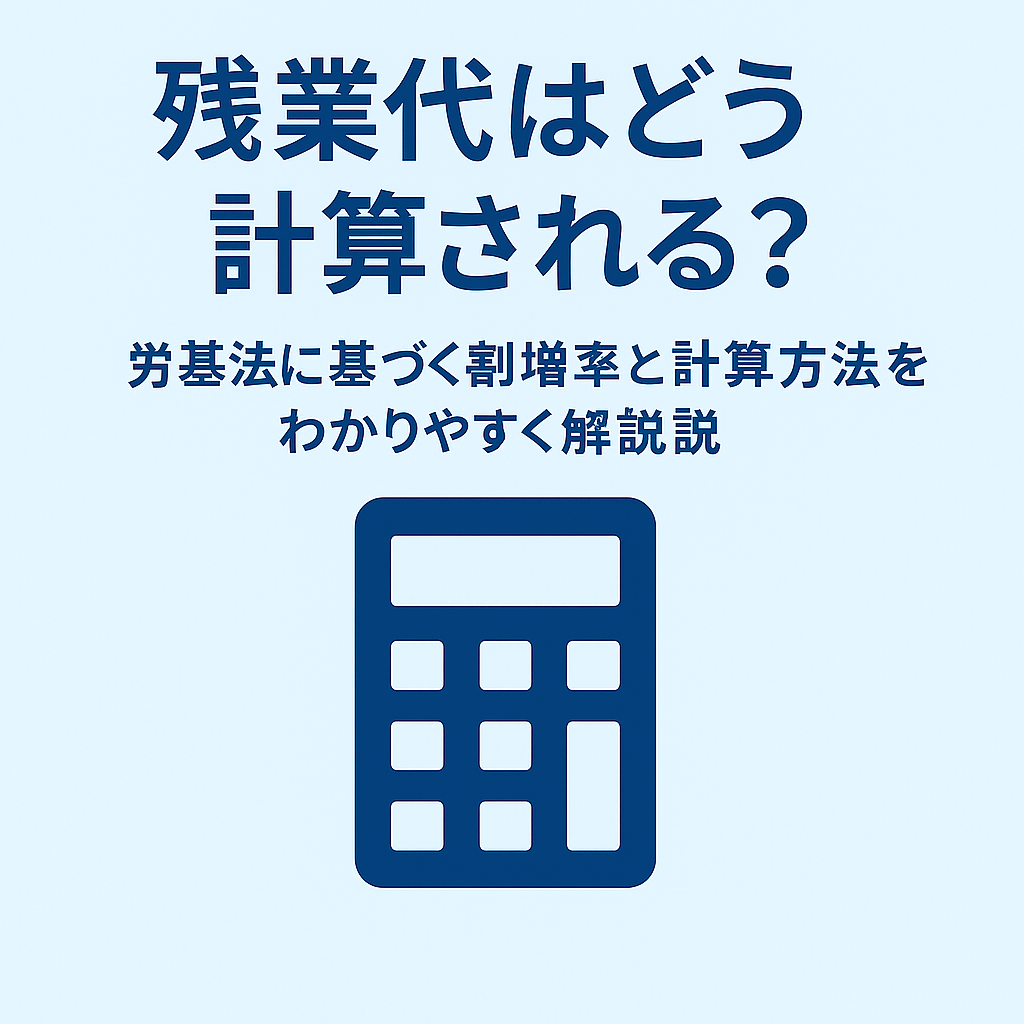
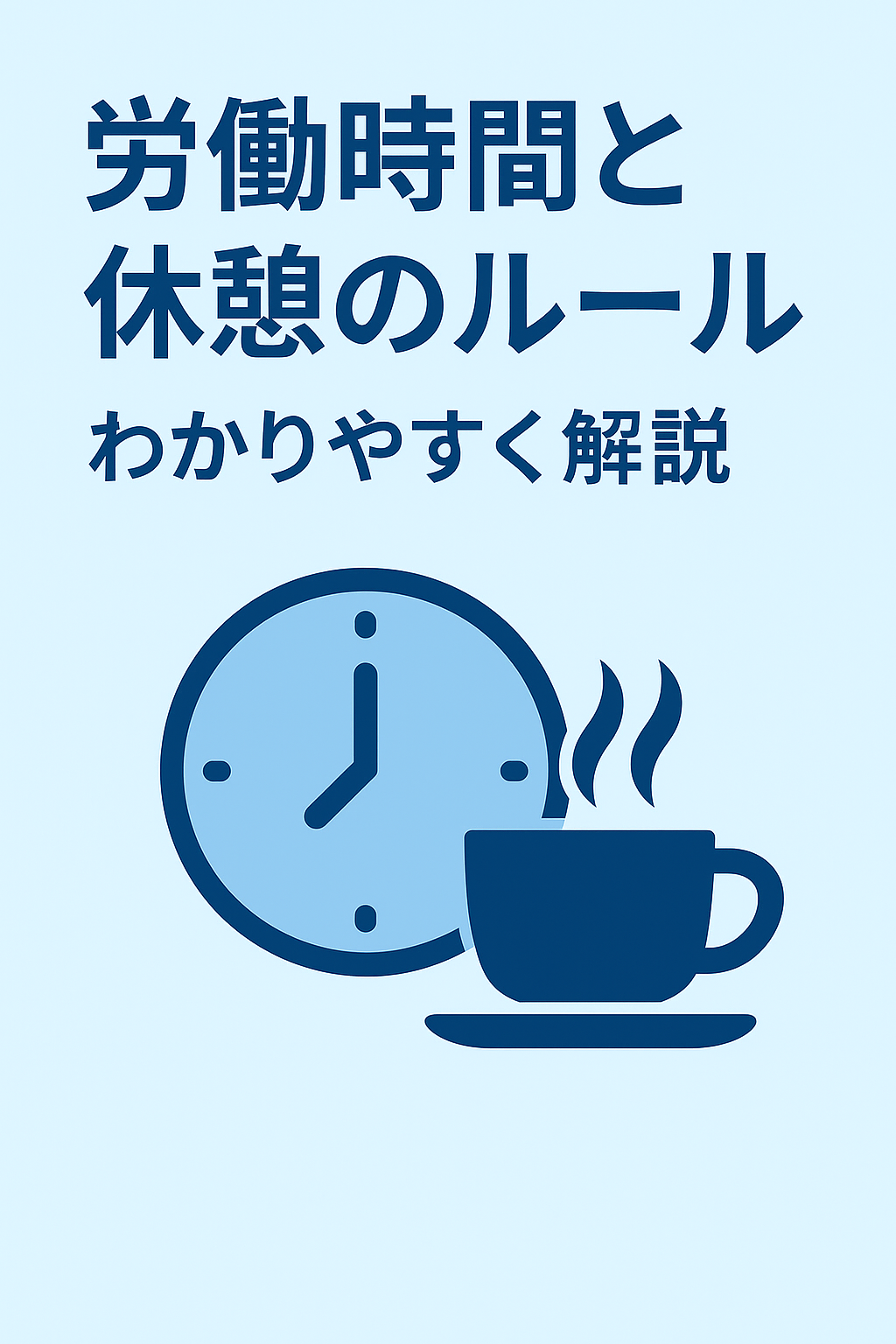
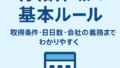
コメント