「会社に向かう途中で事故に遭った」「作業中にケガをした」。どちらも労災保険の対象になり得ますが、通勤災害と業務災害では認められる根拠や判断ポイントが異なります。違いを理解しておくと、いざというときに迷わず正しく申請できます。
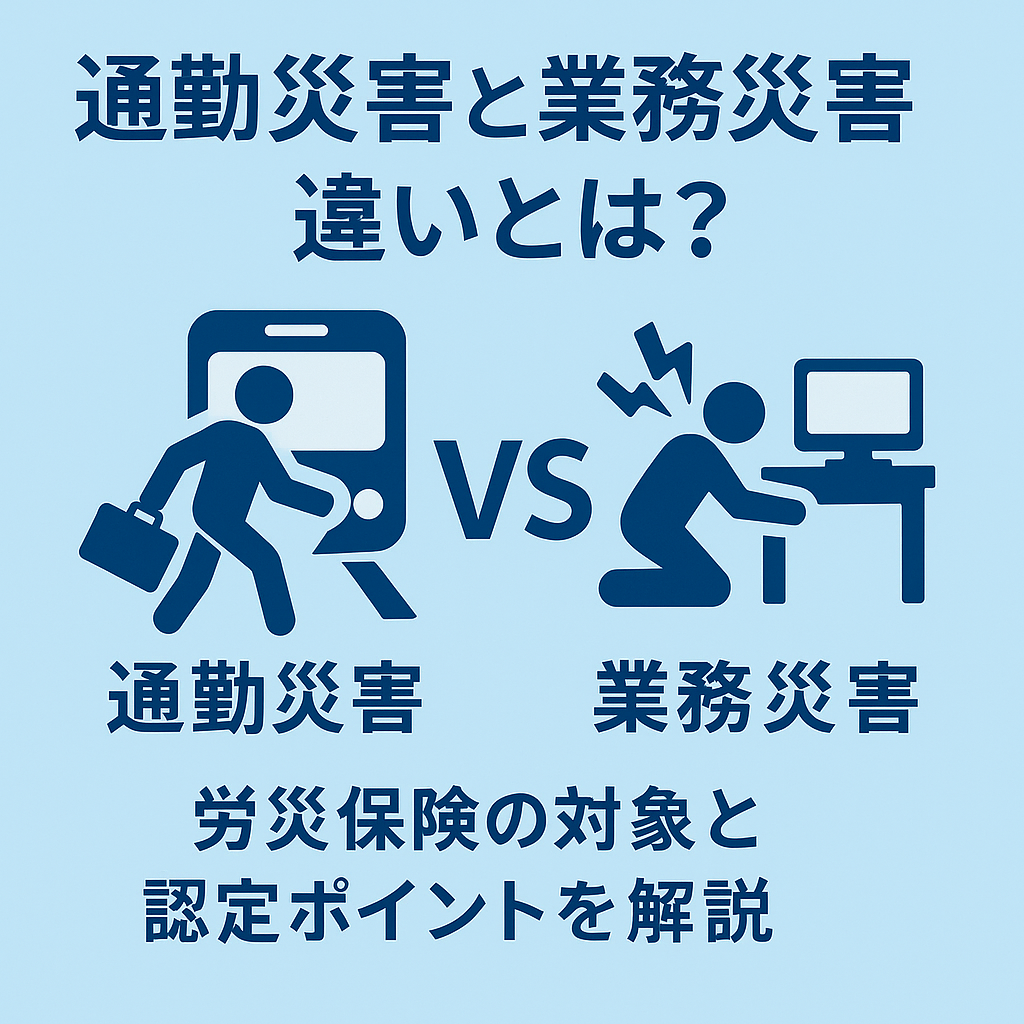
1. 基本の定義
業務災害とは
労働者が業務を遂行中に、または業務が原因で負傷・疾病・障害・死亡した場合を指します。判断は主に
- 業務遂行性(仕事中の出来事か)
- 業務起因性(仕事が原因か)
の2軸で行われます。
例:機械操作中の挟まれ事故/高所作業中の転落/接客中の暴行被害/長時間労働や強い心理的負荷が背景のメンタル不調 など。
通勤災害とは
労働者が住居と就業場所の往復、または転勤・出張・副業先への移動など、就業に関連する合理的な経路・方法で移動中に被った災害を指します。
例:通勤電車での衝突事故/自転車通勤中の転倒/バス待ち中の怪我 など。
2. 認められやすい・認められにくい典型例
業務災害の例
- 認められやすい:指示された残業中の転倒、現場作業中の落下物による負傷、客先対応中の交通事故 など。
- 注意が必要:休憩時間中の純粋な私用行為/就業時間外の私的トレーニングなどは業務との因果関係が弱くなる。
通勤災害の例
- 認められやすい:自宅→会社を最短またはこれに準ずる合理的経路で移動中の事故。
- 逸脱・中断の扱い:
- 日用品の購入・投票など日常生活上やむを得ない行為のための小さな寄り道は、原則として直後に合理的経路へ復帰すれば保護されます。
- 飲み会・娯楽・大幅な遠回り等は保護対象外になりやすい。
3. 共通点と相違点(覚えどころ)
- 共通点:どちらも労災保険の対象。療養補償給付(治療費自己負担なし)、休業補償給付(原則休業4日目から)、障害・遺族・介護補償給付などの枠組みは概ね共通。
- 相違点の核:
- 業務災害=業務遂行性/起因性を丁寧に立証
- 通勤災害=合理的経路・方法からの逸脱・中断の有無が焦点
4. 申請の流れ(通勤・業務どちらも基本は同じ)
- 受診・診断書の取得(初診日・傷病名が重要)
- 会社へ申出(会社経由で所轄労基署に提出。会社非協力でも本人申請可)
- 必要資料の準備
- 業務災害:作業手順書、指示メール、勤怠・残業実績、目撃者メモ 等
- 通勤災害:通勤経路申請、交通系IC履歴、事故証明、地図・時刻表 等
- 労基署の調査・認定
- 給付支給(休業が続く場合は定期的に継続申請)
5. よくあるグレーゾーンを整理
- 出張先での食事中の事故:出張行為と一体(業務の延長)と評価されやすいが、観光目的の大回りなどは否定されがち。
- 会社行事・懇親会:会社の業務としての参加要請が明確なら業務関連性が上がる。任意参加・私的二次会は原則対象外。
- テレワーク中の事故:就業時間内・業務に通常伴う行為かどうかで判断。就業規則や在宅勤務ルールの整備が鍵。
- メンタル不調:過重労働・ハラスメント・重大事故対応など強い心理的負荷の有無が焦点。記録化(面談記録、メール、勤怠)が重要。
6. 証拠づくりのコツ(実務で差がつくポイント)
- 通勤:通勤経路を就業規則に沿って事前申請。ICカード履歴・ドラレコ・タクシー領収書を保管。
- 業務:作業指示・工程表・チャット履歴・監視カメラログなど、業務とのつながりを示す客観資料を残す。
- 体調:受診の初診日を早めに作る/症状日記を付ける。
- 第三者:目撃者メモや上司の承認履歴は効果大。
7. まとめ(一目で違い)
- 通勤災害=合理的通勤経路上の事故か?逸脱・中断の有無が鍵。
- 業務災害=仕事中かつ仕事が原因か?業務遂行性・起因性が鍵。
- どちらも労災保険で手厚い補償を受けられる。迷ったら申請し、労基署が最終判断。
- 日頃から通勤経路の申請、記録の保存、就業ルールの整備を。
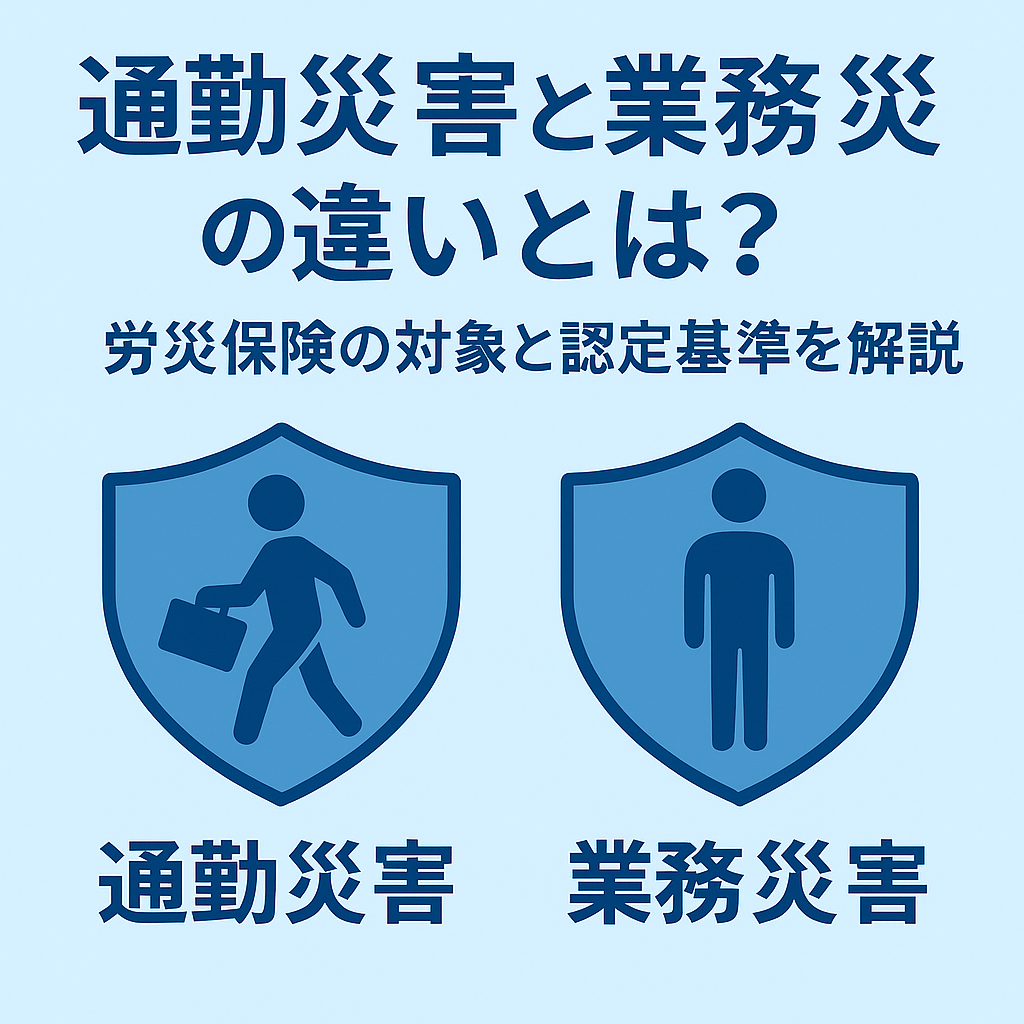


コメント